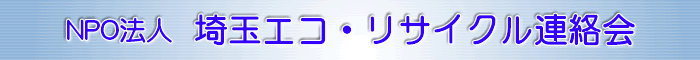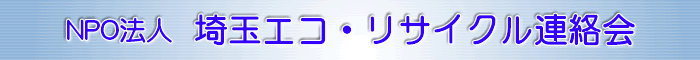|
|
|
|
|
|
エコ・リサ交流集会 第3分科会
産廃処理は変わったか、自然住宅や住まい方を探る
第3分科会は、産廃の約2割を占める建設廃材の減量をテーマに、循環型社会構築の視点から、産廃処理の実態を知るとともに、環境負荷のすくない「住環境づくり」について考えあいました。
まず、元全国産業廃棄物連合会会長で、エコ・リサ会員でもある鈴木勇吉氏から、廃棄物処理法と関係法規について現状と問題点について報告がありました。
鈴木氏は、産廃問題の原因として、
| |
|
| ① |
排出事業者の責任が長く不明確であったこと |
| ② |
数が多く規模も小さい処理業者の数が多いことからくる価格競争の厳しさが適正処理を困難にしてきたこと |
| ③ |
経済的な誘導をせず、そうした不適正な処理が放置されてきたことなど |
| |
|
また、平成12年の法改正によって、管理票導入による排出者責任明示化、野焼禁止、処理場基準の厳正化などの施策がすすむ一方、逆に、処理施設建設が進まず不法投棄に流れている、また、その不法投棄の実態が把握されていないという指摘がありました。
さらに、鈴木氏は、大量生産大量消費という産業のあり方やくらし方をそのままにしては、真のリサイクルはありえない、縦割り行政がわが国の環境対策にとって弊害となっているなどの意見とともに、今後の課題として、一般廃棄物と産業廃棄物の垣根を超えた処理を考えていくこと、処理業界自身の改革が必要であること、そして、排出事業者がさらにきちんと責任を全うしていくこと、などが重要であると述べられました。
次に、狭山市在住で国際的にも評価の高い建築家の泉本晋一氏から、西欧にくらべて寿命が短いといわれる日本の住宅作りの現状と、今後の「住まい」のあり方についての提言がありました。
泉本氏は、戦後の日本の住宅づくりの特徴について、
| |
|
| ① |
コスト優先の考え方からくる制約
-狭い、規格化、スピード、生長の早い木材の多用、化学素材多用 |
| ② |
環境条件の制約-腐りやすい |
| ③ |
主要素材が壊しやすかった-建替え容易、 |
| ④ |
社会の変化が早く住まいへの要求変化が早かった |
| |
|
また、泉本氏は、建築家の立場から、広い敷地が取れない中でも、近隣との共同、素材の選択、外に開かれた設計、などの事例を紹介しながら、エンドユーザーであるわれわれ自身が、「住環境」についての総合的な価値観を確立することが、結果として、環境負荷が少なく長く使用できる「住まいづくり」の近道であると述べられました。
|
| |
|
 休憩後の交流の中では、環境対策における縦割り行政の問題、ゴミ回収の有料化の問題、ツーバイフォー住宅の耐用性と解体処理の難しさの問題、シックハウス症の問題、公共工事における廃棄物処理の問題、排出者の責任の問題などについて、多岐にわたり熱心な質疑と意見交換がおこなわれました。 休憩後の交流の中では、環境対策における縦割り行政の問題、ゴミ回収の有料化の問題、ツーバイフォー住宅の耐用性と解体処理の難しさの問題、シックハウス症の問題、公共工事における廃棄物処理の問題、排出者の責任の問題などについて、多岐にわたり熱心な質疑と意見交換がおこなわれました。
(報告者 山崎育夫氏)
|
| |
|
|
|
|
| |
|